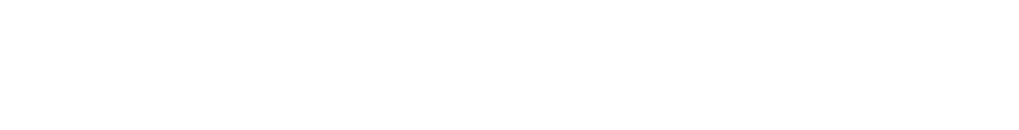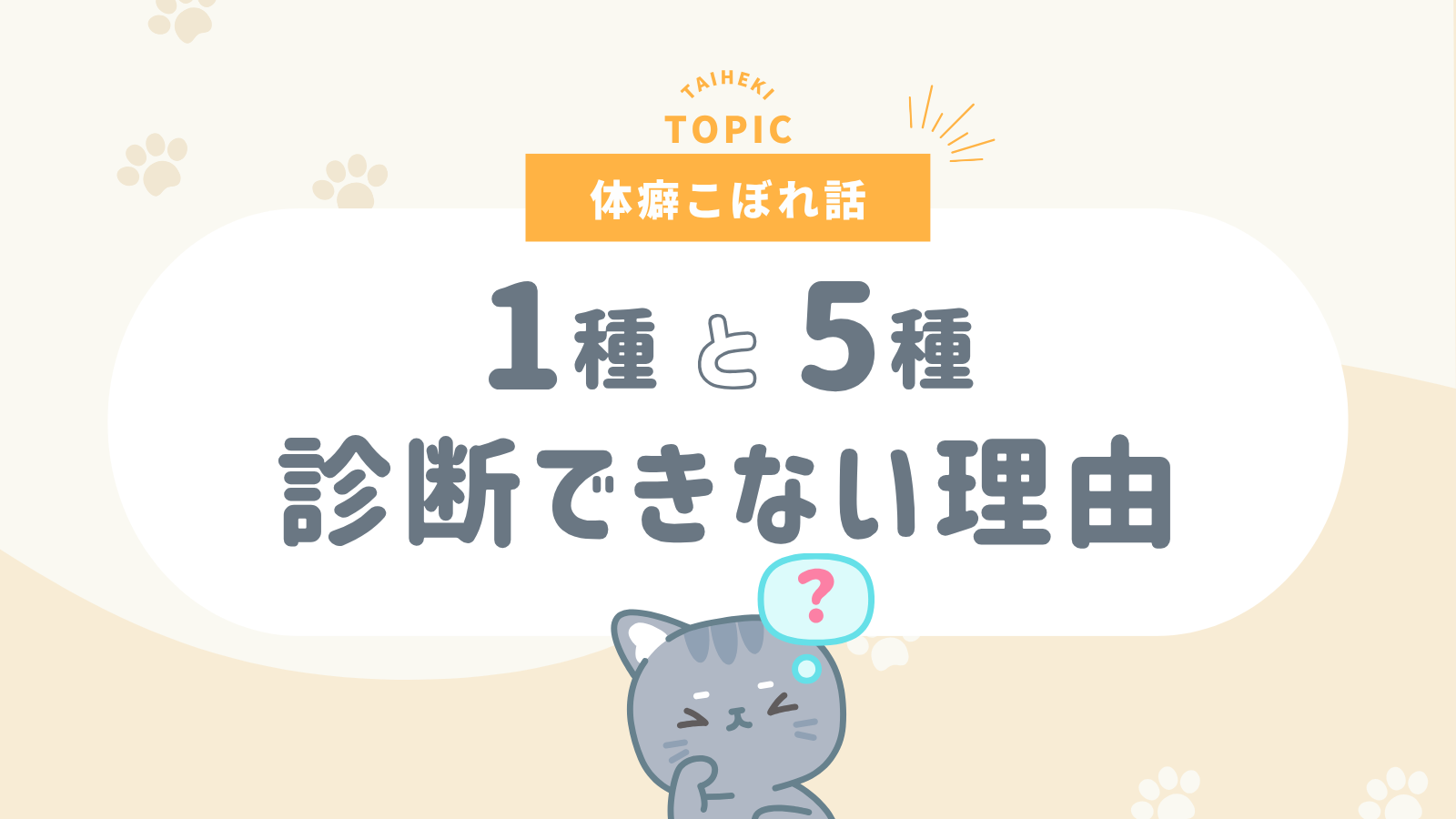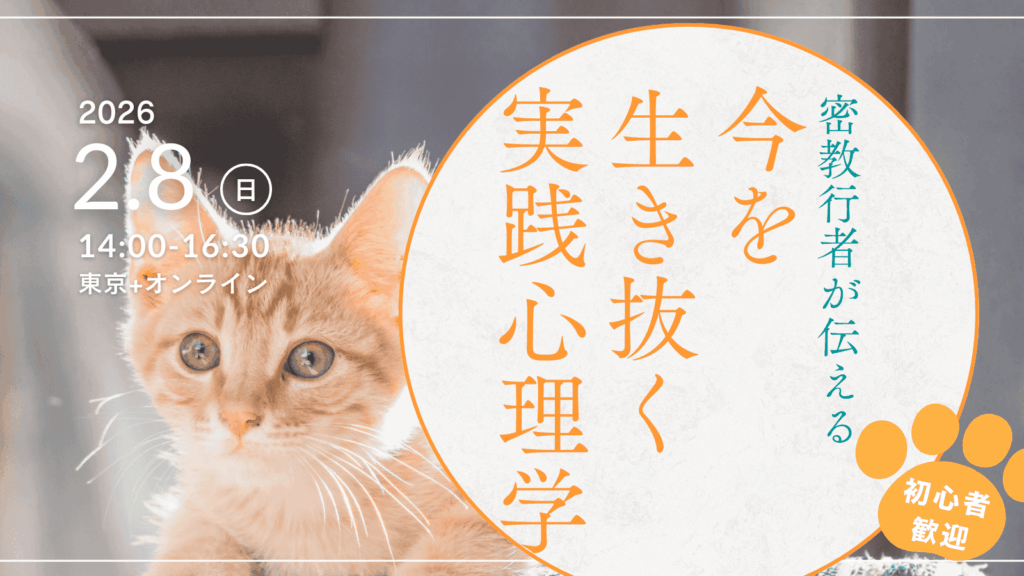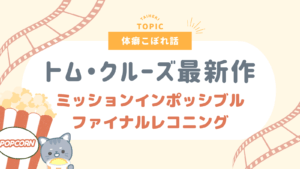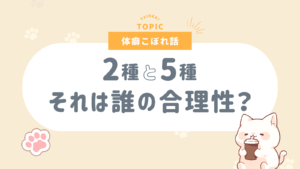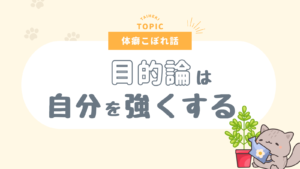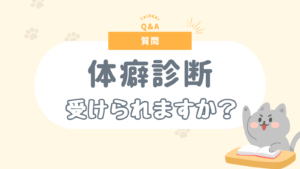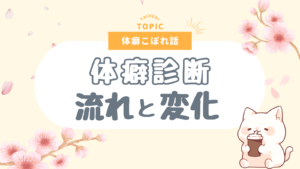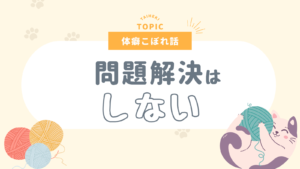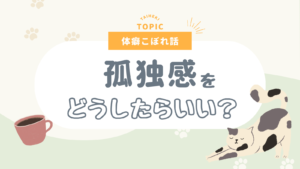こんにちは。体癖はじめの一歩、講師の吉沢です。
「体癖こぼれ話」と題しまして、その時々の気づきをお話していきたいと思います。よろしければお付き合いください。
体癖論で使う言葉を理解するのには、しばらくその世界に浸ってみることがお勧めです。どの業界であってもその点は共通しますよね。
体癖論の面白さは、身体に基づいているという点にあります。
例えば、1種がここぞというときに上に伸びるというのを、胸を張っている5種だと見る向きがあります。これは、文章だけで勉強した方にみられる特徴でもあります。お稽古事は人から学ばなければ修正できないという例です。
しかし、その見方はなるほど観察しようとしたのだなと、理解もできるのです。それもまた私には興味深いのです。1種と5種の体型を叙述すると全く違うように読めるのですが、文章だけを頼りに実際の人間を観察すると、その違いがわからないものなのです。
体癖診断をするのに、体型、感受性、雰囲気を診ると繰り返し伝えています。
体癖論を学んだ方にしてみれば、1種と5種は大きな違いがあるのではないでしょうか?
体型も違いますし、感受性の特徴は真逆と言ってもいいでしょう。
首が太く天に伸びるような首で上半身が柱のような1種、身体がしなやかで呼吸器の強さから胸を張ったスタイルの5種。脳内で思考し計画していると実際には行動しなくても結果が得られたように満足してしまう1種と、動きながらでしか頭が働かず、端的に自分の経済的利害で行動する5種。書く文章も長さも違います。
それにも関わらず、5種は胸を張るという姿勢一つで1種を5種だと診断するのですから、人間を弁別するというのは一体何なのだろうと思います。
最後に、決め手になる雰囲気を検証してみましょう。
1種は知的で品のある地味な人です。5種はスタイリッシュで都会的な人です。あまりにも違う表現ですね。それなのに本や文章だけで学んだり、数回話を聴いてわかったつもりになった人は、必ず1種と5種を混同して診断するのです。体癖論に興味を持つ方の特徴もありますが、真面目さゆえに、木を見て森を見ずになりがちです。
なるほど混同するのもよくわかると思えた頃、ここにこそ体癖論の奥行きを感じるのです。
1種と5種で迷ったとき、運動神経の良さを感じるのが5種という視点も付け加えたいと思います。

体癖のよくある質問にお答えしました!
体癖・心理学を学ぶなら
初心者向けの体癖講座、心理学講座を開催中です。
基本から丁寧にお伝えしていますので、お気軽にどうぞお越しください。